
論理的思考とういうと、理系のイメージが圧倒的に強いですよね。
文系は理系ほど頭を使わないので、論理的思考があまりできないと思われがちです。
でも、実際には方向性が違うだけで、論理的な思考力に差なんてないんです。
文系と理系で、どこが違うのか、文系はなぜ論理的思考ができないと思われてしまうのかを解説します。
【目次】
論理的とは
このブログでも何度か取り上げていますが、論理的というのは、言葉につながりと法則性があるということなんですね。(まだの方はコチラ→論理的な思考力を身につけて、仕事のデキる人になる!!)
数字やデータを使えないと論理的にならないというわけではないんです。
文系と理系では、考えるのに言葉がメインになるのか、数字やデータがメインになるのかの違いがあるだけです。
文系と理系で考える力に差はない
文系は論理的思考ができないかというと、全くそんなことはありません。法律や哲学なんかは、論理的な思考を必要とします。
また、文系は必ずしも数字に弱いということもなく、経済学や会計なんかでは、理系ほどではなくても、計算はやりますし、数字で考えるということもやります。
なので、文系は数字に弱く、論理的思考ができないというのは間違っているんですね。
文系と理系の論理的思考の違い
アナログとデジタル
文系は結構アバウトで、理系は細かく、きっちりしているって言われますよね。
文系はアナログ思考で、少しくらいのズレも許容の範囲内です。
一方、理系はデジタル思考で、誤差は最小限にとどめようとしますよね。
ジェネラリスト指向とスペシャリスト指向
文系は、理系のように一つの分野を深く掘り下げるということが少ないです。
どちらかというと、浅く広くといった感じですね。
理系は専門性が最大の武器なので、狭い分野で高度な知識を身につけようとします。
文系と違って、狭く深くのイメージです。
演繹法と帰納法
思考のスタート地点としては、文系では目標や目的を設定するというところからスタートします。
自分が支持している理論や考え方からスタートして、結論を導きだすという演繹法的な思考をするんです。
これに対して理系では、事実やデータから法則性を見つけ出して、結論を導くという帰納法的な思考をします。
理系では、何が正しいのかを決めるのは、事実やデータであって自分ではないんですね。
結果重視とプロセス重視
文系は途中経過よりも、とにかく結果重視です。
理系と違って、まず結論ありきなところがありますから、途中の経過はあまり大事じゃないんですね。
これに対して理系は、途中のプロセスを大事にします。
答えが出て、その答えが合っていたとしても、途中のプロセスが間違っていれば、その答えは間違った答えとして認められません。
たまたま正しい答えと一致しただけの間違った答えと考えるのが、理系の考え方なんです。
未来指向と原因指向
例えば、為替が変動して、円高や円安になった場合に、それが貿易にどう影響するのか考えますよね。
文系ではこのように、ある出来事が、他の出来事にどう影響を及ぼすのかを考えます。
過去にさかのぼって、なぜ円高や円安になったのかなんて考えずに、これからどうなるのかを考えるという点では、未来指向です。
逆に理系では、なぜそうなったのかという原因を徹底的に追求します。
原因が分かっていれば、結果もコントロールできるし、将来に同じ原因が発生すれば、同じ結果の発生が予想できると考えるのが理系です。
複雑さとシンプルさ
理系では、基本的に原因と結果は1:1の関係で対応していると考える傾向があるので、考え方もシンプルになります。
物事をシンプルに考えるのは理系の特徴だし、理系の人の話が分かりやすい理由の一つでしょう。
逆に文系では、原因と結果は1:1で対応するとは限らず、さまざまな事態を想定して考えるので、考え方は複雑になっていきます。
互いに補い合う関係
思考の違いを比較してみましたが、完全に真逆になりますよね。
これらの思考は、互いに補い合う関係であって、どちらが優れているというものではありません。
考えの流れが真逆になるということであって、文系は論理的思考ができないというわけではないんですね。
文系はアナログ的だから論理的思考ができないと思う人もいるでしょうが、アナログ的でも、思考に「つながり」と「法則性」があれば論理的であると言えるんです。
なぜ文系の方が、論理的思考ができないと思われるのか
文系、理系以外に芸術系がある
ここまで記事をお読みいただければ、文系と理系は方向性が違うだけで、思考力に差は無いというのが、お分かりいただけたと思います。
ではなぜ、文系は論理的思考ができないなんて言われるのか、疑問に思いますよね?
実は、文系と理系という二つに分けるやり方に問題があるんです。
言葉で考える文系、数字やデータで考える理系の他に、感覚で物事をとらえる芸術系が存在するんです。
この芸術系が文系の中に入っているせいで、文系は理系に比べて論理的思考ができないと思われてしまうんです。
文系と芸術系の違い
論理的であるというのは、思考の流れにつながりと法則性があるということなんですね。
文系では、理系との比較でも書いたとおり、思考につながりと法則性があるため、論理的思考ができるんです。
しかし、芸術系は、物事を感覚でとらえるため、論理的思考なんてほとんどやりません。
芸術系は、思考につながりや法則性といったものはなく、論理的というよりも感情的です。
理系と芸術系
理系は数字やデータを使って、物事を具体的、客観的にとらえるのに対して、芸術系は感覚で、物事を抽象的、主観的にとらえます。
科学的な理系に対して、芸術系はスピリチュアルなところがあったりするので、理系とは完全に真逆になります。
芸術系が、まるで文系代表みたいな感じで理系と対比されるものだから、文系は論理的思考ができないと思われてしまうんですね。
正確に表現するのであれば、芸術系は論理的思考ができない、となるんです。
文系の人全体が、論理的思考ができないというわけではないんですね。
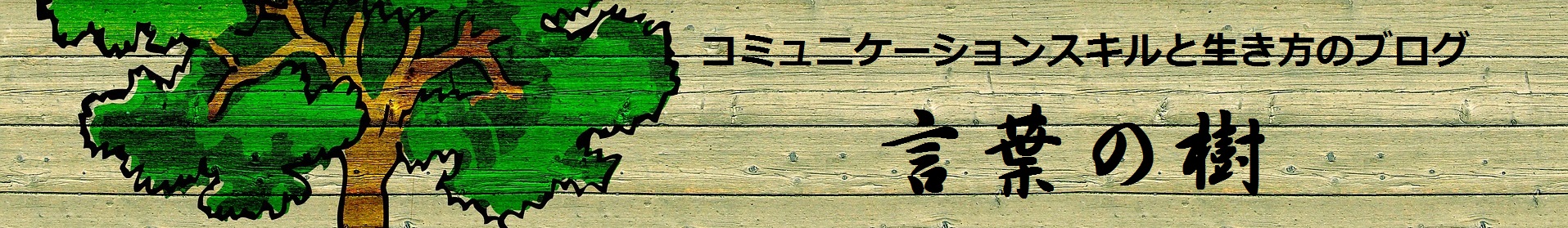
文系は自分が正しいというところからスタートするという説明など、筆者様の文系に対する典型的な誤解が見受けられるので、コメントさせていただきました。
たとえば、英語の文法を例に挙げると、大量の自然言語(いわゆるネイティブスピーカーの話す英語)から、いくつかの共通の性質を抽出し、文法というルールのようなものを設定します。法律も同様に、世の中に生じる問題から、その共通点を抽出し、その問題を解決するためのルールを設定します。正しいか否かではなく、設定をするのです。以上の文系2分野に共通する点として、文系の学問は帰納的な思考のプロセスであると私は考えています。よって、答えさえあっていればプロセスは問わないという解釈も不適切です。
一方、理系の学問は帰納的に設定した公理体系が正しいことを前提に、それに矛盾がないように論理や計算を用いて具象へと還元していく演繹的な学問ではないでしょうか。
そもそも、文系と理系という学問の分け方に正当性はあるのでしょうか。数学の中に統計と確率という分野がありますが、統計は大量のサンプルを用いて推測を行う帰納的なもの、確率は事前確率が正しいという前提でとある事象の確率等を導きだす演繹的なものです。また、英語から文法を見出すことは帰納的なものですが、言語の運用は自然言語との矛盾がないように運用するという点において演繹的です。(言語の場合無意識的な処理を行っているので実感しにくいですが)個人的には、一つの科目についても帰納的思考と演繹的思考の両者を峻別すべきだと思います。
それが、学校教育において公理体系や文法といった抽象化の産物である帰納的思考の帰結を先に与えてしまうことで、筆者様のような誤解が生じているのです。
KOKI SEKINE 様
ご丁寧にコメントいただき、ありがとうございます。
それではご指摘いただきました点について、回答させていただきます。
>文系は自分が正しいというところからスタートするという説明など・・・
こちら、記事の意図としては、文系はまず答え(ゴール)を決めてから、そこから逆算していくという意味で書いております。
まず帰着点を決めてそこからスタートするという意味で、その人にとってのあるべき姿を「正しい」という言葉で表現していたため、SEKINE様に誤解を生じさせてしまったようです。
「正しいか否かではなく、設定をする」とのご指摘通り、まさにこちらの意図としても「設定する」です。
私が誤解しているわけではございませんので、ご安心ください。
表現が不十分で申し訳ございません。記事の方は該当箇所を後ほど修正させていただきます。
>答えさえあっていればプロセスは問わないという解釈
確かに学問的な議論をするのであれば、ご指摘の通り「文系の学問は帰納的な思考のプロセスである」との考えで間違いないと思います。
ただ、注意していただきたい点として、記事の中では学問よりも実務の方に軸足を置いた書き方をしております。
記事の読者としては、入社して間もない文系出身のビジネスパーソンをメインに設定しております。(学生さんでも読めるように、かなりざっくりした書き方になっております。)
したがって、厳密な学問的考え方ではなく、とにかく納期に間に合わせることや結果を出すことに重点を置くというビジネス的な考え方として紹介しています。
そのため、学問的に見れば解釈として不適切ではないかと感じる部分も出てきてしまいますが、学問的な観点で捉えているのか、それとも、実務的な観点で捉えているのかの違いであるとご理解いただければと思います。
こちらからの回答は以上となります。
コメントいただき、ありがとうございました。