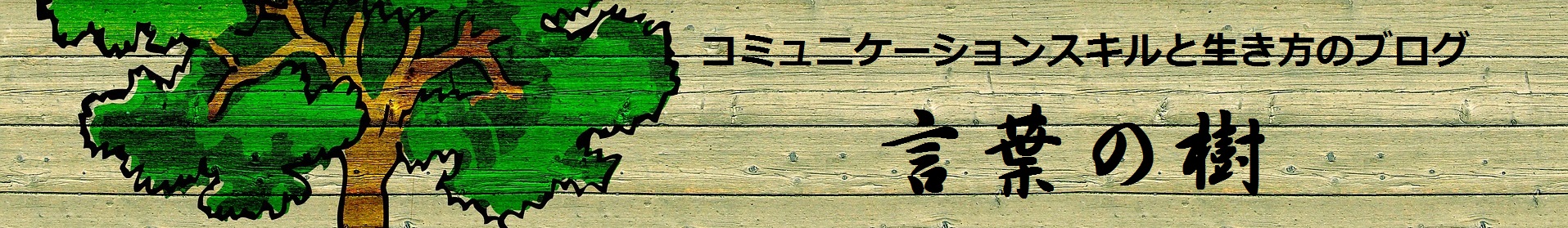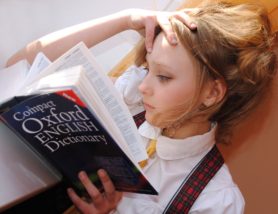
みなさんは、「学力」と聞いて、何を思い浮かべますか?
なんとなく、勉強ができて、テストでいい点数をとる力が学力だと思っているのではないでしょうか。
実は、学力は、働き方が変われば、その中身も大きく変化します。
今回は、キャリアを考える上での学力について取り上げます。
【目次】
時代とともに変わっていく学力
学力といっても、明確なとらえ方があるわけではなく、中身も曖昧です。
「勉強さえできれば、仕事もできるはず!」と思われがちですが、実は、そういうものでもありません。(詳しくは、コチラの記事をどうぞ→論理的思考の違い。勉強ができても仕事ができない原因とは?)
学力と一言にいっても、いつの時代でも同じというわけではなく、時代が変われば、学力の中身も変化していきます。技術革新によって、何をどう学ぶのかは大きく変わってくるんですね。
これまでに、インターネットの普及や、AIの登場などによって、教育の現場にも大きな変化がもたらされました。
では、具体的に、時代とともに学力のとらえ方がどのように変化していったのかを解説します。
インターネットが登場するまで
インターネットが登場するまでは、分からないことがあれば、知っていそうな人を探し出して質問するか、図書館で調べるというのが一般的でした。
そうなると、分からないことを調べるのに、やたらと時間や手間がかかることは、容易に想像できるでしょう。
なので、自分の頭の中に、たくさんの知識を詰め込んでおけば、調べものにかかる時間や手間を節約することができ、それだけ仕事もスムーズにこなすことが可能になります。
こういった背景もあって、学校でも、知識量を重視して、とにかくたくさんの知識を詰め込む、いわゆる「詰め込み教育」が行われていたわけです。
この時代の学力といえば、知識量の豊富さを表していて、テストでも、いろんなことを暗記していれば、いい点数が取れたという感じでした。
働き方としては、ビジネスの現場では、部下よりも、その上司の方が、たくさんの知識や経験を持っており、上司の指示が無ければ、部下は何も判断できないという状態です。
そういうわけですから、基本的に上司が全ての仕事の指示を出し、部下はそれに忠実に従うというのが一般的でした。
インターネット登場後
1990年代の後半に入ると、インターネットや携帯電話が普及するようになり、いわゆる「情報化社会」が到来しました。
知らないことがあれば、すぐにインターネットで調べることができるし、相手の電話番号さえ分かれば、分からないことも知っていそうな人にすぐに聞けるようになったわけです。
IT機器の発達によって、分からないことを調べるという手間が劇的に少なくなり、パソコンがあってインターネットにつながっていれば、いつでも調べられるようになりました。
分からないことなんて、すぐに調べられるようになったわけですから、その結果、知識量の多さは、あまり意味をなさなくなっていきました。
知識量の代わりに重要視されるようになってきたのが、知識の運用能力です。
入試などでも、新学力観問題というものが登場し、教科書を単純に丸暗記しただけでは解けないような問題が出題されるようになりました。
知識なんていくらでも手に入るようになったわけですから、その知識をどうやって活用するのかに重点が置かれるようになったわけです。
インターネットの登場によって、学力は、知識量の豊富さから、知識の運用能力へと変わっていきました。
ビジネスの現場でも、部下はインターネットで分からないことを調べられるようになったわけですから、上司も、いちいち細かいところまで指示しなくなってきます。
だんだんと、指示待ち社員はNGだと言われるようになってきて、自分で考えて仕事を処理できる問題解決型の人が求められるようになりました。
この時代になると、勉強でも仕事でも、考えるということが重要視されるようになってきたわけです。
スマートフォン、SNSの登場
インターネットが登場して間もない頃は、パソコンは持ち運びできないということで、インターネットでの調べものをする場所は、たいていはパソコンが置かれてある場所に限定されていました。
しかし、便利なスマートフォンが登場したことで、どこにいてもインターネットが使えるようになり、さらにSNSを活用すれば、知識やノウハウを持っている人ともつながりやすくなりました。
その結果、単純にいろんなことを知っているということは、ほとんど意味をなさなくなり、知らないことはスマホを片手にいつでも調べられるようになりました。
そして、「知らないことなんて、いつでも調べられる」ということで、知的好奇心もどんどんと下がっていき、学習意欲も落ちていってしまったわけです。
このような中で重要視されるようになってきたのが、本質を見抜く力です。
数学や物理なんかの問題でも、丸暗記は通用せず、公式の意味をちゃんと理解していないと解けないという問題が出されるようになりました。
また、法律関係の国家試験などでも、法律の立法趣旨や基本的な考え方といったことを押さえていないと答えられないという問題も出題されるようになりました。
私が受験した税理士試験では、2010年あたりまでは、丸暗記した教材の内容をそのまま書き出せば、点数がもらえるという状態でしたが、それ以降は、法律の理論をちゃんと理解していないと答えられない問題が出されるようになり、受験生の負担は増えました。
ビジネスの現場では、上司からの指示がなくても、自分で動いて問題点を見つけ、解決していく人材が求められるようになりました。
課題を解決するためには、問題の本質をとらえていないといけません。
なので、勉強でも仕事でも、本質を見抜くということが重視されるようになってきたわけです。
AIの登場
2010年代の後半になると、ディープ・ラーニングという革新的な技術によってAIが飛躍的な進歩をとげ、多くの仕事をAIが人間の代わりにやることが可能になってきました。
すでに答えが存在するような問題であれば、AIに答えを探させた方が、早くて確実ですから、事務処理的なことは全部AIにさせたほうがよくなったわけです。
このような状況の中で、重要視されるようになってきたのが、答えのない問題に対して、答えを出していく能力です。
変化の激しい時代の中では、過去の経験や常識が通用しないことも多く、そのような状況にうまく対処できる能力が求められるようになってきました。
最近では、アクティブ・ラーニングというものが導入されるようになり、従来のように先生が児童や生徒に一方的に知識を教えるのではなく、児童や生徒が自分たちの頭で考えて答えを出すという授業が行われるようになってきています。
ビジネスの現場では、もはや同じ会社に何年もいられるという保証はなく、自分のキャリアは自分で切りひらいていかないといけないという状態になってきています。
不確実な要素が多く、先が読めないという時代では、勉強でも仕事でも、自分で答えを出していくという力が求められています。
これからの時代の学び
2020年からは入試改革によって、大学入学試験の問題は、大きく変わっていきます。
今までは、問題の答えは一つだけというのが常識でしたが、これからは、複数の答えも有り得るし、場合によっては、どう答えたらいいのかわからないような問題も出てきます。
すでに、オックスフォード大学やケンブリッジ大学といった世界の大学では、そういった考えさせるような入試問題が出ています。
オックスフォード&ケンブリッジ大学 世界一「考えさせられる」入試問題:「あなたは自分を利口だと思いますか?」 (河出文庫)
「カタツムリには意識はあるのでしょうか?」や「火星人に人間をどう説明しますか?」といった問題が出されており、一見すると「そんなこと聞いて、どうするんだ?」だとか「どうやって解答を採点するんだ?」と思うような問題ですよね。
こういった問題にも答えていく力こそが、AI時代の学力なわけです。
当然ながら、このような問題に解答するためには、本質を理解する力に加え、かなりの思考力と考えたことをうまく表現する能力が要求されます。
ただ、最近の若い世代は、活字離れで本をあまり読まないため、知識もインターネットから得てきた表面的や断片的なものが多く、思考が深まるということが、なかなかありません。
さらに、文章を書くといっても、そのほとんどはSNS程度の短いものが多く、長い文章を組み立てる能力が、衰えてきているのではと感じます。
なので、このブログでは、そんな人の役に立つようにと、作文テクニックや考え方のテクニックをたくさん取り上げているので、参考にしていただけたらと思います。
これからの時代には、未知なものや、予測不能なものに対処する能力が求められます。
そういった力を身につける学びが、これから重要になってくるんですね。