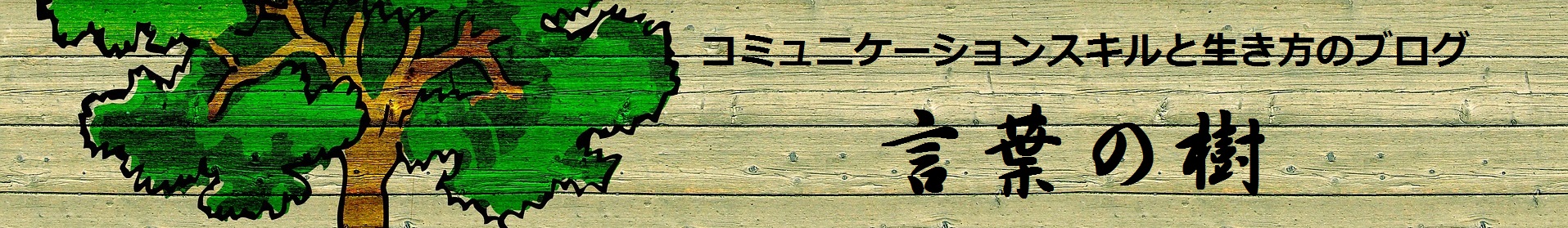みなさん、「還付金詐欺」って、聞いたことありますか?
税金や医療費の還付金の手続きをすると言って相手をATMへ誘導し、お金をだまし取るアレです。
お金を還付すると言っておきながら、一体どうやってお金を払い込ませているのか?
「私は、ちゃんと気をつけているから大丈夫!」と言う人もハマってしまう恐ろしい仕組みと、その対策についてまとめました。
【目次】
前例にとらわれていると、ハマってしまう
みなさんは、「詐欺」と聞くと、どんなイメージが思い浮かびますか?
架空のもうけ話を持ち込んできたり、心当たりのない請求書が届いたり・・・詐欺にもいろいろなパターンがありますが、共通していえるのは、金品をだまし取ろうとすること。
なので、「お金をだまし取ろうとしてくる=詐欺」というイメージがあると思います。
でも、そのイメージを持ってしまっていると、逆に還付金詐欺に引っかかりやすくなってしまいます。
還付金詐欺は、お金を還付しますと言ってくるので、だまし取られそうな感じが全くありません。
従来の詐欺のイメージとは全く異なるため、事前にこういう詐欺もあるということを知っておかないと、「詐欺じゃないから、安心だ」と簡単にハマります。
この辺も、還付金詐欺の巧妙なトリックです。
「詐欺とは、何かトラブルなどを装って、お金をだまし取ってくるものなんだ」という被害者の思い込みを利用し、これが詐欺だと認識されないようにしているわけです。
還付金詐欺に限らず、詐欺も、次から次へと新しいものが出てくるので、従来のイメージに当てはめてしまっていると、新しいタイプの詐欺に対処できません。
詐欺に共通する三つの重要な要素
「新しいタイプの詐欺なんて、どうやって対処したらいいの?」と思うかもしれませんが、詐欺には共通する三つの要素があります。
還付金詐欺の具体的な手順を見る前に、まずは確認しておきましょう。
信用させる
当たり前のことですが、信用が無いと、誰も話を聞いてくれません。
ですので、詐欺師としては、自分の言うことを相手に聞かせるためにも、まずは信用を獲得しようとしてきます。
偽造された身分証明書を使ったり、架空の投資取引でも、最初はちゃんと配当金が支払われたりなど、あの手この手で、自分は信用できるということを、さりげなくアピールしてきます。
相手との間に、信頼関係を構築するというのは非常に重要で、心理学的にはラポール形成と呼びます。
心理カウンセリングなんかで催眠誘導を行う場合には、このラポール形成がないと、相手を催眠にかけることができません。
詐欺師も、巧みに催眠を使ってきますので、簡単に信用してしまうと、催眠にかけられてしまいます。
ですので、簡単に信用してしまわないように、用心が必要です。
焦りや不安につけ込む
焦りや不安も、詐欺師にとっては、相手をコントロールする上で重要です。
人は、焦ってしまうと、目の前のことで頭がいっぱいになってしまい、他のことを考える余裕がなくなります。
その結果、何かおかしなところがあったとしても、それを疑問に思わずにスルーしてしまうんです。
また、不安を煽られてしまうと、人は、自分の身を守る行動に意識が集中してしまうため、他のことを考えることが困難になります。
いずれにしても、正常な意思決定が難しい状態になってしまい、詐欺に気がつきにくくなってしまいます。
無知につけ込む
詐欺師が狙う相手は、社会の仕組みを、あまりよく知らない人です。
ある程度の知識があれば、途中で「ん?何かおかしくないか」と気づくことができます。
でも、あまりよく分からない法律や金融、機械の操作のことともなると、何かおかしなところがあったとしても、気づくことができません。
結果として、知らないからツッコミを入れることができないし、どうしていいのか分からずに、詐欺師の言う通りに動いてしまうんです。
還付金詐欺の具体的な手順と危ないポイント
それでは、詐欺に共通する三つの要素を押さえた上で、具体的な手順がどうなっているのかや、危ないポイント、対策などを解説していきます。
①電話がかかってくる
まず、市役所や社会保険事務所などの公的機関の職員を名乗る人から電話がかかってきます。
そのままですと、電話に出た人は「何で急に電話がかかってくるの?」と不審に思ってしまいます。
そこで、職員になりすました詐欺師は、「以前に青色の封筒をお送りしたのですが、返信が無かったので、ご連絡させていただきました」などと答えて、急に電話したわけではないことを強調することもあります。
このようにして、まずは不信感を持たれないようにします。
その他にも、「還付される金額が、12,450円ありますが、還付の手続きはされますか?」などと聞いてくることもあります。
いかにもありがちな金額を言うことで、相手に「詐欺ではなさそうだ」と思い込ませるわけです。

また、還付の手続きをするのかを聞いてくるというのも、心理トリックです。
一見すると、手続きをするのか、しないのかを自由に選べるように見えますが、実際には、「還付の手続きなんて面倒くさいから、手続きなんてしません!」なんて言う人はいません。
なので、選択肢は、実質的に一つしかありません。
なぜ、わざわざこんなことをするのかというと、自分の口から「還付の手続きをします」と言わせることで、これは自分の意志に基づいてやることなんだということを、被害者の脳に刷り込むわけです。
こうすることで、詐欺師に操られているという感覚がなくなってしまうのと同時に、自分でやると言ったからには、やらなければならないという心理も働きます。
ごく普通の会話のように見えますが、実は、こちらを信用させるための巧妙な心理トリックが仕組まれています。
対策としては、電話番号の確認をしっかりやることが大事です。
可能であれば、電話に出る前に、知らない番号からかかってきた電話は、発信元を特定できない場合には、出ないようにするのが安全です。
②ATMへ誘導される
次に、相手を信用させた詐欺師は、「還付の手続きの期限は今日までですので、今ならまだ間に合います」などと言ってきます。
相手を急がせることで、余計なことを考えさせないようにするわけです。
こうなってくると、電話を切った後で、電話番号を確認するような心理的な余裕がなくなってしまいます。
「大変、時間が無い!急がなくちゃ!!」と頭の中がいっぱいになってしまい、電話番号の発信元を確認しないまま、ATMへ直行してしまいます。
危険を防止するためにも、知らない電話番号から電話がかかってきたら、電話に出ずに、まずは電話番号を検索して発信元を特定してください。
相手を急がせた詐欺師は、さらに「還付の手続きのご案内をします」と、事前に調べておいた被害者宅近くのATMへ行くように指示します。
それなりに知識のある人であれば、「なんで役所の窓口じゃなくて、ATMなの?」と疑問に思うところです。
通常、こういった手続きは役所などの窓口でやるものであり、ATMは全く関係がありません。
しかし、難しい手続きのことなど分からない人にとっては、「そういうもんなんだ」という感覚しかなく、無知につけ込まれるわけです。
相手を急がせることで混乱させ、正常な判断ができないような状態にしたうえで、近くのATMを提示することで、そちらに行くように巧みに誘導してくるんです。
③手順を指示される
指定したATMに相手を誘導した詐欺師は、携帯電話で具体的な操作方法を指示してきます。
その際に、「これから手続きのご案内をしますので、こちらが指示した通りに操作してください。間違った操作をしてしまうと、手続きができなくなってしまいますので、ご注意ください」と言ってきます。
このように言うことで、被害者側には「言われた通りにしなければならない」という心理が働きます。
間違ってはいけないというプレッシャーもあり、それによって思考停止状態に追い込まれます。
急いでいて時間が無い、間違うと手続きできない、慣れていない機械の操作・・・さまざまな要因が重なり、正常な思考力が奪われていきます。
なので、途中で何かおかしいということを感じる余裕もなく、とにかく言われるがまま動いてしまうんです!
よく考えてみれば、少しボタンを押し間違えたくらいで手続きできなくなってしまい、還付金が没収されてしまうなど、おかしな話です。
しかし、無知をつけ込まれた被害者は、そのことに気づくことができず、正常な思考力も奪われてしまうため、何も抵抗できなくなってしまいます。
④詐欺師によっては、いくら搾り取れるのかを確認してくる
手続きの説明が済むと、詐欺師は、ATMの操作を指示してきます。
詐欺師によっては、いくらまで搾り取れそうなのかを確認してきたうえで、その上限ギリギリまで振り込ませようとしてきます。
具体的には、「個人番号を確認しますので、残高参照のボタンを押してもらえますか」などと言ってきます。
そして、「表示された数字を、右から読み上げていってください」と言います。
もちろん、残高参照のボタンを押して表示される数字は、自分の銀行口座の貯金残高です。
ただし、機械の操作に慣れていないうえに、正常な判断力を失った状態の被害者には、そのことが分かりません。
さらに、数字を右から読ませることで、脳の中での情報の照合がうまくいかないようにし、それが金額を表していると気づきにくくするという効果もあります。
このようにして、詐欺師は、被害者に気づかれることなく、被害者の貯金残高を把握するわけです。
⑤振り込ませる
一連の準備が整ったところで、いよいよ詐欺師は、被害者にお金を振り込ませます。
「まず振込みのボタンを押してください」と言われますが、被害者は、それが相手にお金を振り込んでしまうボタンだとは気づきません。
正常な判断力を奪われているという部分もありますが、機械の操作に慣れていないために、「振込み」というのが、相手から自分の口座にお金を振り込んでもらうためのボタンだと勘違いしているという部分もあるんです。
振込みのボタンを押させた後は、振込先の銀行名や支店名を入力させます。
その後、金額を入力するところで「今から言う識別番号を入力してください」などと言ってきます。
もちろん、これは識別番号などではなく、こちらから相手の口座に振り込まれてしまう金額です!
振込みが完了すれば、詐欺師側が「一週間以内に入金されますので、ご確認ください」などと言って、電話を切って終了です。
催眠にかけられると、抵抗できない
「自分はちゃんと気をつけているから大丈夫だ!」という人もいますが、ほんの少し注意した程度では、防ぎきれません。
自力で逃れるチャンスがあるのは最初だけです。
それを逃してしまい催眠にかけられてしまうと、正常な思考力が奪われてしまうので、抵抗できなくなります。
後になればなるほど、深い催眠にかけられてしまい、逃げ出すのが困難になります。
だから、いくら注意を呼び掛けても、なかなか減らないわけです。

しかも、詐欺師が催眠を使ってくるということを知っている人など、ほとんどいません。
催眠に対しても、ほとんどの人は、目の前で糸に吊るした5円玉や懐中時計をブラブラさせて、「あなたは眠くな~る」と暗示をかけていく程度の理解しかありません。
私もNLPと呼ばれる心理学を通して催眠を学びましたが、普段目にする広告など、日常のあちこちに、さりげなく催眠が使われています。
催眠は、事前にそれが催眠であることを認識しておかないと、防ぎようがないんです。
「ちゃんと気をつければ、なんとかなる!」という精神論は通用しないということを、知っておきましょう。
詐欺師が使う催眠への対策とは
「催眠なんて、防げるのか?」と思うかもしれませんが、ちゃんと防ぐ方法もあります!
催眠は、相手を暗示にかけて動かしてしまう強力なパワーを持っている一方で、暗示にかけられる前であれば、ツッコミを入れてやると簡単に無力化することもできてしまいます。
例えば、「○○ランキング1位!!」というフレーズがあったとしましょう。
広告なんかでメチャクチャよく見かけるフレーズですが、実はこれ、催眠です。
これをそのまま受け入れてしまうと、「ランキングで1位になるくらいだから、きっとすごいに違いない!」という思い込みが生じ、買って損はないという暗示にかかってしまいます。
しかし、ツッコミを入れてやると、自分が思っているほどたいしたことがないんじゃないかということが分かってきて、催眠が無力化されていきます。
例えば・・・
・それって、どういう基準で選ばれてるの?
・1位だった期間って、いつからいつまでなの?
・どんな人が選んでるの?
・競合する相手は、どれくらいいるの?
・競合相手の強さは?
・・・という具合です。
具体的な範囲や能力なんかが明確になってくると、思い込みが無くなっていきます。
催眠の基本は、相手の思い込みを利用することなので、思い込みをする余地がなくなれば、それだけ催眠にかからなくなります。

他にも、「みんな買ってる!!」というフレーズに対しても、「“みんな”って、具体的に誰?」とツッコミを入れると、意外と「みんな」の数の少なさにビックリすることもあります。
いつも、誰でも、多数、大人気・・・こういった過度な一般化や、範囲が不明瞭な言葉というのは、特に注意が必要です。
相手を催眠にかけるためには、相手との信頼関係を形成することが重要になってきます。
なので、とにかく簡単に信用せずに、質問をやりまくって、どこまで信用できるのかを徹底的に確認するということも大事です。
詐欺師は、やたらと質問の多い相手を嫌がります。
簡単に相手を信用しないようにし、必要な知識(手続きやATMに関すること)を事前に身につけておいた上で、「それ、おかしくないですか?」とあちこちにツッコミを入れてやれば、撃退することは可能です。
焦らされてしまうと、おかしなところがあっても気がつかなくなってしまうので、落ち着いて対処するということも重要です。
徹底した確認と質問で、相手に隙を与えないようにしましょう。
詐欺を防ぐ3つのポイント
詐欺に共通する三つの要素をご紹介しましたが、これは、裏を返せば、詐欺を防ぐためのポイントでもあります。
相手を簡単に信用しない、焦って対応しない、必要な知識を身につける。
この3つが、詐欺を防止する重要なポイントです。
とりわけ、必要な知識を身につけるという点においては、ATMを操作する必要があるのは、相手の口座にお金を振り込む側であって、入金してもらう側は、ATMなど操作する必要はないということを知っておきましょう。
単に詐欺の手口を学ぶだけでは、新しいタイプの詐欺が出てきた時に対処できません。
どんな詐欺がきても対処できるように、三つの要素と詐欺を防ぐポイントは、ぜひとも押さえておいてください。