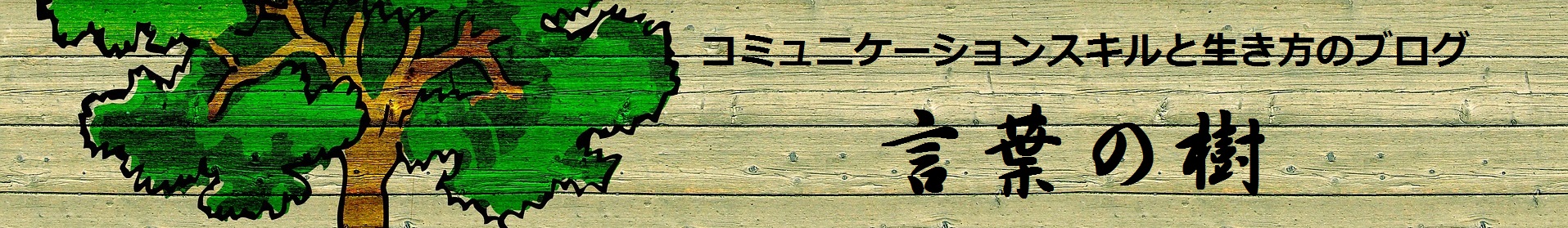コミュニケーション能力といえば、どこの企業でも必ずと言っていいほど、必要とされるスキルですよね。
「私は、コミュニケーション能力が高いです!」ということを、面接でうまくアピールできれば、採用される可能性がグッと高まります。
でも、ちょっと気をつけておかないと、自分ではコミュニケーション能力が高いと思っていても、面接官から見て「それ、違うんじゃないの?」と思われることがあります。
面接で注意すべき、認識のズレとは・・・
【目次】
コミュニケーションに対する認識の世代間ギャップ
私が、コミュニケーション能力のとらえ方に世代間のギャップがあると気づいたのは、キャリアコンサルタント講座のスクーリングでのこと。
応募者役と面接官役に分かれて模擬面談をした際に、私が応募者役をして、50代くらいの方2名が面接官役をしました。
コミュニケーション能力のアピールのところで、ブログの運営やアフィリエイトのことについて少し触れてアピールしましたが、面接官役の方からは、「それって、違うよね」とツッコミが入り、思わず「え?」と思ったのがきっかけです。
どうして認識がズレてしまったのかをさぐってみると、どうも世代によってコミュニケーションに対する考え方が異なっているようなんですね。
SNSの登場によって、コミュニケーションのあり方が大きく変わったということもあり、手紙や電話が主流だった世代とFacebookやLINEのようなSNSが主流な世代とで、考え方に違いがあります。
では、具体的に、どのように異なっているのかというと・・・
手紙や電話が主流だった世代のコミュニケーション能力

面接官役の方の言葉で、特に印象に残っていたのが、「コミュニケーションの基本は、直接会うことだよね」ということ。
直接会わずに、文章だとか、電話、パソコンなんかの機械を通してやり取りをすると、気持ちがちゃんと伝わらないし、相手の気持ちもよく分かりません。だから、直接会ってやり取りするということが大事だというわけです。
昔の主なコミュニケーションツールといえば、電話、手紙、メールです。電話では、相手の声だけしか伝わってきませんから、声だけで相手を判断しないといけませんよね。
相手の表情や置かれている状況が全く見えないと不安になってしまい、「どうしても、電話は苦手だ!」と感じる方も多いはず。
また、手紙やメールも、文章だけで相手の感情を正確に読み取るというのは、けっこう難しいこともあります。なので、相手の気持ちを正確に理解するためには、直接会う必要があるわけです。
手紙やメールの場合は、書き上げてから相手が読むまでに時間差があるので、リアルタイムで感情を共有するには無理があります。なので、直接会うということによって、いっしょの空間を共有することができ、感情もリアルタイムに伝わります。
そうすると、信頼関係も芽生えやすくなるんですね。
この世代にとっては、電話やメールでしかやり取りしてこない人というのは、会うのを嫌がっている人というふうに思われるんです。ちゃんと会わなければ、まともなやり取りはできないわけですから、直接会うことが基本になってくるわけです。
SNSが主流の世代のコミュニケーション

SNS世代にとっては、直接会うということは、それほど重要なことではありません。中には、直接会うことを面倒臭がる人だって、いますよね。
Facebook、Twitter、LINE、ブログなど、多彩なコミュニケーションツールがあり、スマホもありますから、どこにいてもリアルタイムでやり取りすることは可能です。
直接会わなくても、SNS上に写真や動画をアップすることができますから、手紙や電話なんかよりも、相手のことがよく分かります。
会ったことがない相手でも、フォロワー数や「いいね!」の数、ブログのPV数なんかで、相手の信用度がどれくらいなのかが分かるんですね。
さらに、SNS上では、友達申請がきたり、同じグループどうしでつながったりなど、直接会わなくても人脈はどんどん広がっていきます。わざわざ会いに行かなくても、バーチャル空間上で、いくらでも親しくなれてしまうんですね。
だから、直接会うということは、SNSを普段からよく使う世代にとっては、あまり重要ではないわけです。
面接でアピールする時のポイント
面接担当者が、あまりSNSを使ったことがない世代であれば、SNSに関するアピールはやらない方がいいでしょう。
この世代は、直接会うことなしに、仕事上のやり取りを全て完結させるという感覚があまり無いので、人と会わずに仕事をするということの理解が難しいんですね。
でも、最近では、アフィリエイトなんかで稼いだり、フリーランスを仲介するサイトを通じて、お客様と直接会うことなしに、サイト上でやり取りを済ませることだって、できるようになってきています。
この世代間の感覚のズレを意識することなく、「自分はSNSをバリバリに使いこなせているから、コミュニケーション能力が高いです!」という感じでアピールしてしまうと、自滅してしまうことになりかねません。
なので、認識のズレに引っかからないようにするために、コミュニケーション能力の共通点をアピールしましょう。
仕事をする上で大事なコミュニケーション能力とは、まず相手のことをよく理解し、その上で、相手のニーズに合った対応ができる能力のことをいいます。
コミュニケーション能力が高いというと、しゃべるのが上手かったり、プレゼンが上手かったりといった印象を持つ人もいます。でも、仕事をする上で大事なのは、そういったプレゼン能力ではなくって、相手のニーズを満たす能力なんですね。ビジネスでは、相手のニーズを満たすことによって、対価としてお金をもらっているわけですから。
アピールする時も、困っている相手の問題点をちゃんと理解して、それに的確に対処して、「助かりました」や「ありがとうございます」と感謝されたというエピソードを交えながら、コミュニケーション能力をアピールすれば、面接担当者も納得するはずです。
うっかりズレたアピールをしてしまうと、担当者側の人に「この子は、分かっていないな」と思われてしまうので、そこは注意しましょう!
認識のズレに気をつけよう
「SNSを使いこなす能力って、コミュニケーション能力に入るんじゃないの?」
SNSでのやり取りが当たり前だと感じる人にとっては、そう感じるかもしれません。でも、自分がそう思ってアピールしても、相手にとってそれが当たり前でないのなら、受け入れてもらえないんですよね。
コミュニケーション能力の基本は、まず相手を読むことです。相手を的確に理解したうえで、それに合うようにアピールしないといけないんですね。
面接の担当者は、どんな考えを持っていそうなのかを考えた上でアピールしましょう。とりわけ上の世代ほど、直接会うことが基本だと考える傾向があります。
自分が当たり前だと思っていても、相手にとっては当たり前でないこともあるんですね。
フォロワーの数が多かったり、「いいね!」をたくさんもらえていたりしても、コミュニケーション能力が高いと評価してもらえない場合もあるということには、要注意です。
相手がどう受け止めるのかを考えずにアピールすると、「う~ん、それ、違うと思うよ」という返事がくるかもしれませんので、気をつけましょう。