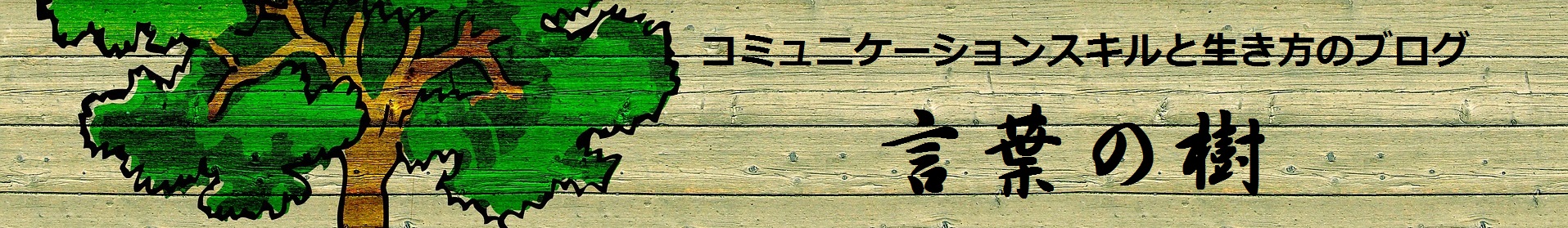前回は、四柱推命は本当に当たるのかを、実際に占ってもらって検証してみました。
でも、「他の占いに比べて、本当に当たりやすいのか?」って、気になりますよね?
そこで今回は、他の占いと比較してみて、四柱推命がズバ抜けて当たるのかどうかを検証してみました。
四柱推命以外に、どんな占いがあるのか?
占いにも、いろいろと種類がありますが、大きく分けると次の3種類に分かれます。(前回の記事では、個人的な見解で3つのタイプに分類しましたが、こちらは一般的に言われている見解です。)
・命(人生全体の運の流れをみるもの)
・卜(一時的な出来事を占うもの)
・相(人相や手相など、ものの見た目から運勢の状態をみるもの)
四柱推命は、生年月日と生まれた時刻から人生全体の運の流れを見る占いなので、命の占いです。
今回の検証では、あまりにもかけ離れた占いだと比較がやりにくいので、比較の対象として、四柱推命と同じ系統の命の占いを選びました。
星座占いについては、運勢の判断が12通りしかないということで、運勢の分類が少し雑だということ、さらにバーナム効果と呼ばれる心理効果によって当たったように感じているだけという面もあるので、除外しています。
四柱推命以外の命の占いで、よく当たると言われているのが、紫微斗数、算命学、六壬神課です。
実際に占ってもらって比較できればいいのですが、これらの占いは四柱推命に比べると、使える先生がかなり少ないので、市販されている本をもとにして、比較してみました。
紫微斗数
使用書籍:『紫微斗数占星術奥義』、東海林秀樹著、学習研究社
紫微斗数は、結構マニアックな占いですが、台湾や香港では四柱推命をしのぐほどの勢いで広まっているらしいです。
これが書かれてある時点で、四柱推命を占いの帝王だと言っているのは、日本だけなのではと感じます。
紫微斗数には、12の占いのテーマ(宮)があって、各宮を表すマス目にどんな星が入るかで、吉凶を判断します。
運勢の判断に使う星が39個もあり、星を求めるための表の読み取りは大変ですが、命盤を作ってしまえば、後は楽です。
テーマが分かれていて見やすく、浅く広くいろんなことが分かるといった感じです。
実際に占ってみた結果としては、四柱推命と似たり寄ったりでした。
算命学
使用書籍:『基礎からわかる算命学の完全独習』、有山茜著、日本文芸社
算命学は、一言で言うなら、四柱推命をより細かく精密なものにしたという印象の占いです。
四柱推命と同じ命式を使いますが、それに加えて、宿命図というものがあります。
四柱推命に比べると、かなり細かく、得られる情報も多いという感じです。
特に、生き方で参考になる部分が多く、私の場合はよく当たっているせいか、本が付箋だらけになるほど。
内容が難しすぎて使えなかった部分もありますが、四柱推命に比べれば、得られる情報量も多く、特に生き方については参考になることが多かったです。
六壬神課(十二天祥星占い)
使用書籍:『安倍晴明秘占 十二天祥星占い』、小野十傳著、学習研究社
六壬神課は、陰陽師にとっては必修とされた占いです。
陰陽師が使っていたと聞くと、なんだかすごそうな感じがしますよね。
この占いは、奥の手として使う占いらしく、使っている先生も少ないです。
四柱推命とは違った少し複雑な命式図を作ります。
運勢の分類がかなり細かく、720通りもあるので、かなり細かいところまで分かります。
この720通りのパターンも、さらに2パターンに分かれるので、合計で1440通りにもなります。
12星座占いに比べれば、かなり細かいですよね。
なんとなく当たる四柱推命に比べると、こちらは当たり外れが激しい印象です。
占いは通常、曖昧な言い回しが多く、どちらかハッキリしないというようなことがありますが、この六壬神課では、「何で、そこまで細かく分かるの!?」というくらい、ズバッと書かれてあってビックリしました。
ただ、念のために自分の身の回りの人のことも占ってみたところ、自分と同じように激しく当たる場合もあれば、「それはさすがに無いやろ~」と思うものもあったりと、当たりハズレは激しかったです。
野球のバッターに例えるなら、ホームラン狙いのフルスイングという感じ。当たればホームランでも、外せば派手に三振です。
奥の手として使われているという理由も、これで納得です。
的中率に違いはあったか?
四柱推命と同じ系統の占いで比較検討してみましたが、四柱推命がズバ抜けてよく当たるというわけではありませんでした。
いろんなことが網羅的に分かるという点では、紫微斗数、情報量が多く、生き方で参考になることが多いという点では、算命学、「これは、すごい!」という当たった時の感動という点では、六壬神課がよかったと思ってます。
結局、的中率では四柱推命が一番だと言えるものではありませんでした。
比較してみて分かった、四柱推命が「占いの帝王」である理由
四柱推命は、他の占いに比べて、ズバ抜けてよく当たるというわけではありません。
それにも関わらず、何で「占いの帝王」なのか、気になりますよね。
実際に他の占いと比較してみると分かりますが、四柱推命って他の占いに比べると、命式を作るのに、あまり手間がかからないんです。
占い師の先生は、たくさんの人の鑑定をしないといけないので、あまり一人の人に手間や時間をかけていられないんですね。
そんな使いやすさもあってか、使っている先生は多数います。
どれくらいたくさんいるのかを、私の手元にある日本占術協会の占術家名鑑(平成17年版)をもとにまとめると・・・
| 占い | 人数 | 割合 |
| 四柱推命 | 169人 | 57% |
| 算命学 | 12人 | 4% |
| 紫微斗数 | 8人 | 3% |
| 六壬神課 | 5人 | 2% |
| タロットカード | 79人 | 27% |
※名簿に載っている294名のデータをもとに作成。
データは少し古いですが、割合はあまり大きくは変動していないでしょう。
また、日本占術協会に加入していない占い師の先生もたくさんいるかもしれませんが、どんな占いがどれくらいの割合で使われているのかを推定する分には問題ないでしょう。
このデータからは、四柱推命が圧倒的多数だと分かります。それだけ四柱推命が使いやすいということなんですね。
同じ命の占いでも、算命学、紫微斗数、六壬神課は、かなり少数派です。
四柱推命に比べると、結果を出すのに手間がかかり、それだけ鑑定料も高くついて、お客さんも来にくくなるというのが、少数派になっている原因のようです。
ちなみにですが、四柱推命は運勢をピンポイントでみることができません。
例えば、明日の試験でいい点数をとれそうかや、好きな人に告白しようと思うが、うまくいきそうかなど、短期的にどうなりそうなのかを鑑定することは、四柱推命にはできないんです。
四柱推命は、あくまで人生全体の運勢を鑑定するものですから。
なので、短期的な運勢を見る際には、タロットカードや五行易(竹串などを使って吉凶を出すもの)などを使って鑑定します。
私が四柱推命の検証で2番目に占ってもらった先生がこのパターンで、四柱推命で分からないところは、タロットカードで占っていました。
四柱推命一つでなんでも分かるというわけではなく、たいていは複数の占いの組み合わせで鑑定するんですね。
四柱推命が「占いの帝王」と呼ばれるのは、そこそこ当たる的中率に加え、使いやすいからというのが理由のようです。