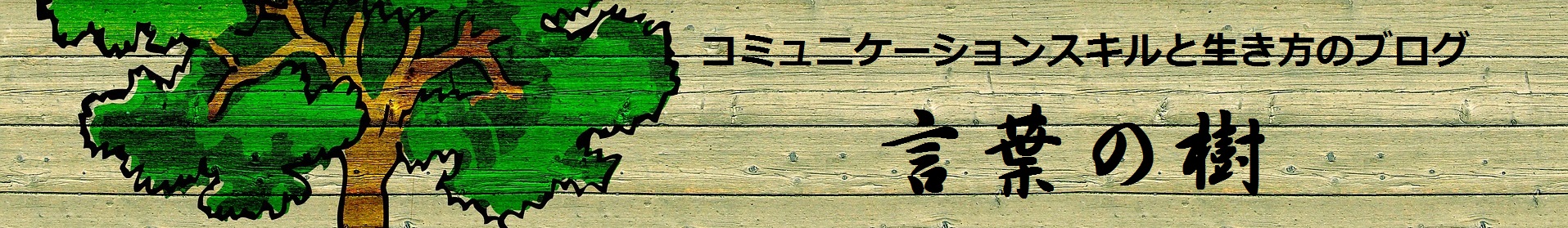格差の問題を論じる上で、必ずと言っていいほど出てくるのが「自己責任論」。
「貧困の原因は、本人にある!」、「努力次第で、貧困からは十分抜け出せる!」という考え方は、根強くあります。
でも、本当に貧困の原因は、その人の努力不足なのでしょうか?
貧困は自己責任とは言えない理由を、確率や心理学の視点から解き明かしていきます。
【目次】
トランプを使った格差社会の再現実験
格差が自己責任ではないことを、どうやって証明するのか?
さすがに膨大なデータを集めて分析するといったことは、手間もかかりますし、難しい理屈など理解できないという人は、たくさんいます。
格差を説明できる確率の理論もあるのですが、「数式なんて無理!」っていう人もいますよね。
そこで、難しい数式などを一切使わずに、誰でも直感的に分かるように、トランプを使ったゲームで説明します。
まずは、写真のように、ハート、スペード、ダイヤ、クラブのカードを絵柄ごとに数字の順番どおりに並べ、エース4枚を手札に加えます。

このエース4枚を裏返してシャッフルし、一枚を選びます。
そして、選ばれた絵柄と同じカードを、一枚手札に加えます。
ここでは、ダイヤが選ばれましたので、ダイヤのカードを新たに手札に加えます。

増えた手札を裏返してシャッフルし、一枚取り出して、同じ絵柄のカードを一枚加える。
この作業を何度も繰り返していきます。
たったこれだけです。
これを繰り返していくと、一体どういうことになるのか・・・

上の写真は途中経過のものですが、クラブのカードは、全然出ていないというのが分かりますよね。
手札にはクラブのカードは一枚しかなく、他の絵柄のカードばかりの状態ですので、この状況では、クラブのカードに勝ち目はありません。

最終結果はどうなったのかというと、上の写真の通り、スペードが一番先にキングのカードにたどりつきました。
クラブのカードも、うまい具合に一枚だけ引き当てたものの、力の差は圧倒的です。
どのカードも、スタートの時点ではチャンスは平等だったものの、途中から力の差がどんどん開いていき、最後には圧倒的な差がついてしまう様子が分かると思います。

念のためにもう一回やってみましたが、その結果が上の写真です。
スタートしてすぐに、ハートとダイヤのカードを連続して引き当てたため、最初の時点で力の差がついてしまいました。
スペードとクラブのカードは、ほとんど出番なしです。
最初にチャンスを手にしたものが、さらにチャンスを引き寄せていき、圧倒的な成功を手に入れることができる。
これが、このゲームが表現している、格差社会が出来上がる仕組みです。
次から次へと手札に加えられるカードは、実績、経験値、お金を表しています。
先に実績、経験値、お金を手に入れた者が、それをもとにして、さらに力をつけていくというのが、お分かりいただけるのではないでしょうか。
トランプさえあれば簡単にできますので、興味のある方はやってみてください。
格差の理由を説明する数学的原理
なんとなくですが、格差が出来上がっていく仕組みを、直感的に理解できたのではないでしょうか。
それでは、ここで少し、数学的な解説を加えておきます。
チャンスが平等なゲーム
もし、このトランプのゲームで、新たに加えるカードを手札に加えずに、絵柄ごとに用意した箱の中に入れていくというルールだったらどうなるのか?
手札はずっとエースのカード4枚のままなので、どの絵柄も、引き当てられる確率は4分の1のまま変化しません。
何度やっても、それぞれの絵柄に、チャンスは平等に与えられます。
このように、一度引き当てたものを、そのまま元に戻して、もう一度同じように選ぶ作業を、復元抽出と呼びます。
復元抽出では、取り出したサンプルをそのまま元の状態に戻すので、最初に取り出したサンプルが、次のサンプルに影響を与えるということがありません。
なので、やればやるほど、力の差がついていくということがないんです。
チャンスが不平等になるゲーム
一方、今回説明に使ったトランプのゲームはというと、やればやるほど、力の差がついてしまいます。
スタートの時点では、それぞれの絵柄に、力の差はありません。
しかし、同じ絵柄のカードを連続して引き当ててしまうと、そのカードと同じ絵柄のカードが手札にどんどん追加されていくので、力の差がどんどん開いていきます。
このように、取り出したサンプルを戻す際に、そのサンプルと同じ種類のものを追加して戻し、さらにサンプルを取り出すという作業をすると、前のサンプリングが、次のサンプリングに影響を及ぼしてしまいます。
何度も取り出されたものほど、有利になれるわけです。
なので、今回ご紹介したトランプのゲームのように、有利になるカードと不利になるカードとで、結果が二極化していくんです。
これが、格差が生じる仕組みを、数学的に説明したものです。
実績があるものを選ぶ心理
格差が生じる数学的なイメージが、なんとなくつかめたのではないでしょうか。
ここではさらに、心理学の観点からも解説をしていきます。
かなり強力な損失回避の心理
みなさんは、商品やサービスを購入する際に、何を基準に決めますか?
多くの人は「買って損した!」なんて状態になりたくないので、他の人の口コミや、どれだけ売上実績があるのかをチェックします。
なので、十分な実力があったとしても、売上実績が全くない人のところには、お客さんはほとんど来ないんです。
とにかく損をしないような行動をとろうとする心理は、人間の防衛本能に基づくもの。
だから、お客さんは、実績の乏しい相手は敬遠し、逆に、実績No.1の方には、吸い寄せられるようによっていきます。
行動経済学の研究によると、人間は、利得よりも損失の方を、3倍強く感じるという結果もあります。
それだけ、損失回避の心理は、自分の命を守ることにつながるものなので、人間は、安心感を持てないものには近づきたがらないんです。
この損失回避の心理によって、実績を上げているところには、さらにお客さんが集まるようになり、実績がないところとの差が、大きく開いていくことになるわけです。
日常にあふれる実例

日常の例でいうと、新聞やネットの広告なんかでは、売上No.1やランキング1位などという言葉がたくさん並んでいますよね。
多くの消費者は、そんな宣伝文句に誘われて、その商品やサービスを購入します。
就職活動なんかでも、社名は知られていないけど、素晴らしい技術力を持った中小企業よりも、誰もが社名を知っているような大企業に人気が集中します。
ここでも、損をしたくない、安全を確保したいという心理が働き、安心感が得られる商品、サービス、企業に人が集まっていくわけです。
それに加えて、仲間外れになってしまうのは嫌だという集団同調の心理も働くので、他の人と同じ行動をとってしまうようになり、実績No.1や売上No.1に吸い寄せられていくんです。
ネットが格差を助長する仕組み
格差や二極化が叫ばれるようになったのは、インターネットが普及してからです。
「インターネットが、どうやって貧困や格差を生み出してるの?」ということについて、インターネットが登場する前と後を比較して見ていきましょう。
インターネットが登場する前
インターネットが登場する前の情報源といえば、チラシ、近所の口コミ、各家庭に備え付けられたタウンページと呼ばれる電話帳などです。
何か仕事を頼みたいことがあったら、タウンページにその地域の業者の連絡先が業種ごとにまとめられているので、自分でよさそうだと感じたところに電話をかけて問い合わせ・・・という感じで仕事を依頼する相手を探すというのが、この時代の主なやり方。
業者の側も、近所で悪いウワサを立てられると、すぐに商売ができなくなります。
仕事を受注するにも、地元の人との信頼関係が重要で、ランキングよりもコネ重視なところもありました。
業者間では、全国規模で競争するということもないので、仕事が平等にいきわたっていたわけです。
インターネットが登場した後

今ではインターネットがあるので、知りたい情報や分からないことは、検索すればすぐにサクッと解決できますよね。
口コミやランキングも一目でチェックが可能!
適当に検索ワードを入力して検索すれば、あとは検索エンジンが、その検索ワードに最も適した情報を提示してくれます。
なので、多くの人は検索エンジンを信用して、検索結果のトップにばかりアクセスするわけです。
検索結果の2ページ目や3ページ目を見ることって、あまりないですよね?
実際に、私もこうしてブログ運営していて分かることですが、検索結果の1位にはアクセスが集中します。
検索順位が下がるに従い、アクセス数も指数関数的に減少していき、上位3位がほぼ独占します。
検索結果の上位に表示されると、それだけ多くの人の目に何度も触れやすくなるもの。
そのようにして接触回数が増えると、好感度もアップするという効果もあります。(心理学的には、ザイアンス効果といいます。)
検索エンジンが選んできたものを無条件に受け入れてしまうことに加え、ザイアンス効果という心理学的な効果もあり、検索結果の上位に行けばいくほど、利益を独占できるようになるわけです。
こうして1位になれた人には、仕事が集中するようになり、利益の大部分を独占します。
お金は一カ所に集まっていく

1位の持つアドバンテージは、計り知れません。
1位の座を手にした人には、抜群の知名度や実績によって、仕事もお金も集まっていきます。
そして、このようにして集まったお金を運用すると、さらにお金は膨らんでいきます。
お金が、さらにお金をどんどん引き寄せていくという状態に・・・。
お金は、お金のある場所に集まっていくと言われていますが、まさにブラックホール化現象です。
お金は、集まれば集まるほど、他のお金を吸い寄せる力が強くなっていきます。
株や不動産などでお金を運用して増やしていけば、格差はさらに開いていきます。
格差は本当に「自己責任」なのか?

「私は、何も悪くない!」。
ちゃんと努力してきたのに、貧困に陥ってしまった人であれば、そう思いますよね。
そうです!何も悪くありません。
理由は、この記事で解説したとおりです。
最初はたいした力の差など無くとも、ふとしたことがきっかけで、大きな力の差がついてしまう。
それが問題点なのです。
ひとたび差がついてしまうと、挽回することなどできません。
だから、今の社会のルールを、もっとフェアなものにしていく必要があるんです。
あなたは、何も悪くありません。