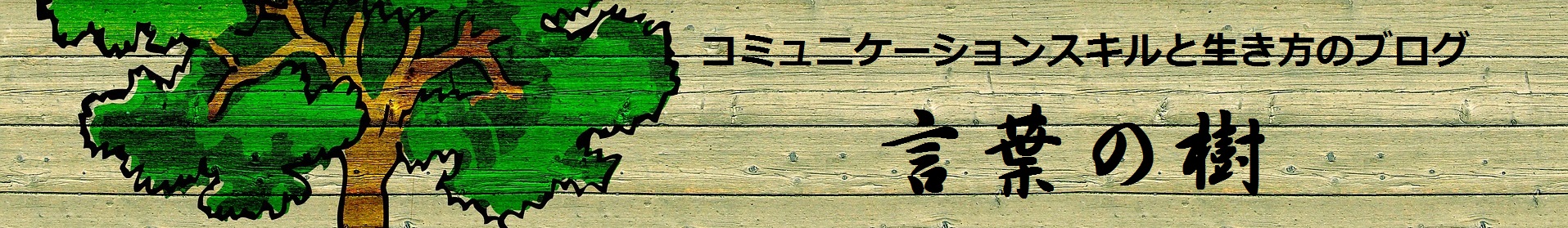こちらがちゃんと伝えたことを、相手にすぐに忘れられてしまう。そうした経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。
今の時代には、情報が洪水のようにあふれています。そのような中で、どうやって受け手の印象に残るように情報発信をすればいいのか?
次から次へと新らしい情報が流れてくる中では、相手に自分のことを覚えてもらうというのは簡単なことではありません。
一度相手に伝えたとしても、すぐに新しい情報で上書きされていってしまい、相手の頭の中から消えていってしまうということも起こりやすいものです。
そこで大事になってくるのが、繰り返し伝えることです。
表現技法の中にも同じ表現を繰り返す「反復法」と呼ばれるものがあり、詩をはじめ様々なジャンルで活用されています。
ただ、繰り返し伝えるやり方の難点として、適切にできないと相手から嫌がられてしまいます。
心理学的な観点も踏まえて、どのように伝えれば効果的であるのかや、感情をうまく表現して相手の印象に残るようにするにはどうすればいいのかについて解説していきます。
「反復法」とは
反復法については、ほとんどの人は学校の国語の授業で一度習っています。
まずは小中学校の復習もかねて、反復法はどんな表現技法なのかを解説していきます。
反復法とは
反復法とは、言葉をうまく使って伝えたいことを効果的に伝える修辞法(レトリック)と呼ばれるものの一つです。その名の通り、同じ語句やフレーズを繰り返し用いることで、伝えたいことを強調したり、リズミカルに表現できるようになります。
主に詩で使われることが多い技法ですが、欧米ではスピーチの中でも用いられることも多くあります。
反復のパターン
反復法の使い方としては、「早く、早く!」のように、同じ語を間に何も挟まずに繰り返すものが中心です。
こうした同じ語を重ねるものは日常会話でも多く用いられており、畳語法と呼ばれています。
その他にも、隣り合った節の先頭や最後の部分で同じ語を繰り返す首句反復や、結句反復、パラグラフの間に繰り返す語を挟む形で繰り返すものがあります。
反復法は、必ずしも同じ語を繰り返すというわけではなく、同義語や類語を繰り返した場合も反復法として扱われます。
ただ、この記事の中では、実用性も考慮して深掘りはしません。
この記事の中では、わかりやすさや使いやすさも考えて、同じ語を反復するパターンについて解説していきます。
反復法を使った表現例
反復法は詩に限らず、日常生活やアニメ、ビジネスなどのスピーチの中でもよく見られます。
どのような効果があるのかを、具体的な表現例を用いて解説していきます。
感情の強調
反復法は、特定の言葉を繰り返すことで、その状態などを強調するという効果があります。
例えば、以下のような表現です。
例1 「いやぁ、今日は暑い、暑い!」
普通に「今日はすごく暑いですね」と表現すると、まるで一般論として言っているようにも聞こえ、どこか他人事のような印象も出てきます。
一方で、「暑い、暑い!」と繰り返すと、暑さがその人にとって耐えがたいもので、言った本人が暑さでまいってしまっている様子というのが伝わりやすくなります。
言い方を少し変えるだけで、言った本人がどう感じているのかという印象は、がらりと変わります。
他にも、感情を強調する例としては、以下のような表現もよく見られます。
例2 「これってもしかして・・・」「違う、違う!俺じゃない!!」
「違う」というワードを繰り返すことで、自分がやったのではないということを強く相手に伝えようとしているのがわかります。
また、疑いを向けられたことに対する驚きや焦りも、表現できます。
他の例も見てみましょう。
例3 「私の料理、おいしい?」「うん、おいしい、おいしい」
料理がおいしいか聞かれたことに対して、「おいしい」というワードを強調しておいしかったことを伝えています。
ただ、この場合はちょっと特殊で、おいしかったことを強調していても、本心ではおいしくなかったのを隠しています。
正直においしくなかったことを伝えると相手の機嫌を損ねてしまうため、相手を傷つけないためにもこのような表現になるわけです。
ドラマチックな雰囲気を出す
反復法は、単に繰り返して相手の印象に残りやすいようにするだけでなく、臨場感を出したり、感情を強調する効果もあります。
それでは、具体的な表現例を見てみましょう。
例4 「フェスティバル会場は、どこへ行っても人、人、人だった」
「フェスティバル会場には、大勢の人がいた」と表現することもできますが、それだとなんだか距離を置いて客観的にながめているような感じになります。
「人、人、人」と繰り返すことで、右を向いても、左を向いても、後ろを振り返っても人がいたという感じで、人で埋め尽されていた様子だけでなく、人ごみの中を移動しているかのような臨場感も出てきます。
例5 「読める、読めるぞ!」
この例文は、元ネタを知っているという読者の方も多いのではないでしょうか。
『天空の城ラピュタ』で、ムスカ大佐が石板に書かれている古代文字を読み取るシーンのセリフですね。
このように繰り返すことで、読めた時の驚きや喜びの大きさや感情の高まりが表現されています。
例6 「ザクとは違うのだよ、ザクとは!」
これも感情を強調した例文ですが・・・世代感が漂ってますね。(すみません。)
このセリフは、機動戦士ガンダムの第12話で、グフというモビルスーツに乗ったランバ・ラル大尉が、アムロ・レイが操縦するガンダムと戦った時のものです。
ザクというのは、ガンダムに興味のある人なら知っている人も多いですが、敵役の中では弱い存在です。(いわゆるザコキャラ的存在)
そんな弱いザクとは一緒にするなという「なめるなっ!」という感情のこもったセリフです。
伝説的なスピーチでの反復
聴衆に何かを伝えるスピーチの場面においては、反復法は効果的です。
ここでは、スティーブ・ジョブズがスタンフォード大学の卒業式で行った、伝説とまで言われているスピーチについて紹介します。
例7
最終号の裏表紙には、早朝の田舎道の写真が載っていました。かなり冒険好きな人なら、ここでヒッチハイクしてもおかしくないような種類の道です。写真の下にはこんな言葉が書かれていました。「ハングリーであり続けろ。愚か者であり続けろ」。それが、彼らが終刊するにあたっての、お別れのメッセージでした。「ハングリーであり続けろ。愚か者であり続けろ」。そして、私はいつも、自分自身そうありたいと願い続けてきました。そして今、皆さんが卒業して新たな人生に踏み出す際にも、皆さんがそうあってほしいと願っています。ハングリーであり、愚か者であり続けてください。
ご清聴ありがとうございました。
(引用)『スティーブ・ジョブズ伝説のスピーチ&プレゼン』、朝日出版社、P89
これは、スピーチの締めくくりの部分です。
ジョブズが卒業生に伝えたかったメッセージ「ハングリーであり続けろ。愚か者であり続けろ」(Stay hungry, stay foolish.)が反復されています。
反復法によって得られる効果
反復法は簡単にできるという手軽さだけではなく、以下のような効果も期待できます。
伝えたいことが相手の記憶に残りやすい
スピーチなどにおける反復の一番の目的は、聞いている人にとにかく覚えてもらうことです。
よほどのインパクトがないと、一発で相手の印象に残るようにするのは非常に難しいものです。
一番伝えたいこと、覚えてもらいたいことを反復して伝えることで、聞いている人の印象に残るようにすることができます。
聞く側としても、大事な部分を何度も繰り返し言ってもらうことで、特に重要な部分はどこなのかということが理解しやすくなります。
また、大事な部分を反復することで、うっかり聞き漏らす人が出てきてしまうということも防ぐことができます。
脳にとっても、同じ情報が繰り返し入ってくることで、記憶に残りやすくなります。
信頼の獲得につながる
毎回話す内容がコロコロ変わってしまうと、周囲の人から八方美人のように思われかねません。
相手からの信頼を獲得するためには、言っている内容に一貫性があるということが重要です。
反復していれば、主義・主張が一貫しているという印象を与えられます。
また、繰り返し見聞きするものに対しては警戒心が薄れて親近感がわいてくる「単純接触効果」により、受け手に安心感が生まれるということも期待できます。
こうした安定性や安心感によって、とりわけビジネスなどの分野においてはリーダーとしての信頼につながりやすくなります。
話を区切る効果もある
反復法のちょっと意外な使い方ですが、話の切れ目にあたる部分で使うようにすると、どこに話の区切りがあるのかを相手に伝えられるようになります。
受け手としては、どこからどこまでが一つのまとまりなのかというのが把握しやすくなり、頭の中で情報の整理がしやすくなります。
そうしたことから、演説で使われることもあります。
キング牧師の「I Have a Dream.」は有名ですね。
公民権運動に大きな影響を与えたキング牧師の演説は、1963年8月28日にリンカーン記念館で行われたものだそうですが、修辞の傑作としても高い評価を受けています。
「I Have a Dream.」は首句反復として用いられており、この「I Have a Dream.」から次の「I Have a Dream.」までが一つのまとまりとなっています。
聞き手としては、どこからどこまでが情報のまとまりなのかが分かりやすくなり、頭の中を整理しやすくなります。
反復法を使うことのデメリット
反復法は、スピーチやSNSの発信などで簡単に使えますが、以下のようなデメリットもあります。
攻撃的な印象を相手に与えやすい
反復法では、同じ言葉を繰り返し使います。そのため、同じことをあまりにも何度も言っていると、主義・主張が強い人であるかのような印象を周囲に与えやすくなります。
日本においては、控え目であることが美徳とされ、空気を読む文化があります。何度も言わずに一回だけにしておくのが良いとされ、繰り返すのはくどいというように受け止められやすいものです。場合によっては、何も言わずに、雰囲気で伝えるということさえあります。
また、使う言葉によっては、受け手側が価値観の押しつけや命令のように感じやすくなるということもでてきます。
受け手に攻撃的な印象を与えてしまっていないかは、十分配慮する必要があります。
しつこいと思われるとブロックされる
内容が攻撃的なものではなかったとしても、繰り返す頻度が高すぎると問題が出てきます。
特に、メディアで流れてくる広告がそうです。SNSや動画に出てくる広告をうっとうしいと感じる人は多いはずです。
どうしても売ろうとして消費者の視界にグイグイ入り込もうとするため、それが不快感を生んでしまいます。
また、X(旧Twitter)で、「何度も言うけど」という書き出しで始まる投稿があまりにも多くてブロックやミュートしたという方も多いのではないでしょうか?
こうした書き出しはユーザーの注目を集めやすく、簡単にインプ数を稼ぐことができます。
ところが、たくさんインプ数が欲しいからと調子に乗ってやりすぎてしまうと、ブロックやミュートされてしまいます。
そうなると、かえってインプ数が落ち込んでしまうという結果になってしまいます。
飽きられると聞き流される
反復法では同じ内容を繰り返すため、どうしても単調な感じになってしまいます。
そうなると、簡単に飽きられてしまう可能性も出てきます。
「前と言ってること同じだな」と思われると、相手の注意を引きつけるのも難しくなります。そうなってくると、受け流されてしまうことも多くなります。
飽きさせないためには、表現の仕方やタイミングを工夫することで、受け手の注意を引きつけられるようにすることが重要になってきます。
反復法の効果を最大化させる使い方
反復法は、誰でも簡単にできる表現方法です。
一方で、うまく使えないと、相手に圧を与えてしまい嫌がられてしまいかねません。
反復法を上手に活用し、効果がもっとも発揮される具体的な使い方について解説していきます。
二回と三回の使い分け
まず、何回繰り返せばいいのかについてです。
感情を強調した表現するのであれば、単純に二回重ねるだけです。
先ほどの例文でも見た通りですね。
一方で、相手の記憶に残るようにするためには、最低でも三回は繰り返すということが重要になります。
私はマジックが趣味ですが、マジックの世界においても、相手に暗示を与える際には、三回繰り返すことが重要だとされています。
どうして三回なのかというと、無意識的に人間の脳は、一回や二回程度の刺激なら、「単なるノイズかもしれない」と判断して積極的に記憶しようとしないからです。
ところが、三回目の刺激が来ると、「きっとこの刺激は重要なもので、四回目や五回目も来る可能性が高い」と判断し、重要な情報として記憶しようとします。
こうしたことから、相手にしっかり覚えてもらいたければ、最低三回は繰り返し伝えるということが重要になります。
時間的な間隔の開け方
ここでは相手に確実に覚えてもらうにはどうすればいいのかについて、心理学的な観点から解説します。
長期間にわたって覚えておいて欲しいことがあるのであれば、一度に繰り返し伝えるのではなく、時間間隔を開けて伝えることが重要になります。
マーケティングの世界では、「セブンヒッツ理論」と呼ばれるものがあります。
消費者が、あるメッセージに七回接すると記憶に残り、好意を抱きやすくなって、行動(問い合わせや購入)につながりやすくなるというものです。
脳科学的に見ても、間隔を開けて同じ情報が脳に七回インプットされると、神経細胞同士のつながりが強くなることで長期記憶が形成されることが知られています。
SNS、特にX(旧Twitter)では、タイムラインにどんどん情報が流れていってしまいます。読み手に覚えてもらいたいのであれば、間隔を開けて七回繰り返すというのは意識しておきたいポイントです。
わかりやすいメッセージにする
受け手に覚えてもらいたいのであれば、メッセージのわかりやすさも重要です。
難しい言葉を使ってしまうと、受け手の興味が薄れたり、敬遠されてしまったりといったことが起こりやすくなります。
短く、わかりやすく、できればリズミカルなものにすることが望ましいです。
同じ言葉を繰り返し伝えるにしても、興味を持ってくれた人でなければ、理解しようとも覚えようともしてくれません。
不特定多数に向けた発信であれば、使う言葉のレベルとしては、中学生でも理解できるくらい、可能であれば小学生四年生くらいでも理解できるようなものにすることが理想的です。
「反復法」を使う際のポイント
それでは最後に、反復法を使う上で注意しておきたいポイントについてまとめておきます。
無意識の否定につながらないように注意する
反復が嫌がられやすい理由の一つとして、受け手が否定されているように感じてしまうケースがあります。
たとえば、「早く、早く!」と言った場合に、受け手は無意識的に「どうしてそんなに遅いんだ?」と言われているように感じてしまい、否定されているような気持になることがあります。
内容や状況によっては、攻撃的な印象を相手に与えてしまう可能性もあるので、そのへんは気をつけておく必要があります。
最適な頻度、タイミングを意識する
先ほども解説したように、反復するうえでは最適な頻度や間隔というものがあります。
そこからずれていってしまうと、相手に不快感を与えやすくなってしまい、嫌がられてしまいます。
同じ言葉を繰り返し伝える時には、最適な頻度とタイミングを意識することも重要になります。
くどいと思われないように工夫する
同じ言葉を繰り返すと起こりやすいのが、受け手に「あぁ、またこれか・・・」と思われてしまうことです。
同じ刺激がくるので慣れてしまい、どうしても「飽き」が生じやすくなります。
そうならないためにも、一工夫することも必要になります。
ジョブズのスピーチが、まさにお手本です。
「ハングリーであり続けろ、愚か者であり続けろ」というメッセージが、さりげなく三回繰り返されています。
もし単純に三回繰り返してしまうと、なんだか押しつけがましい印象を与えてしまいます。
先ほどの例文で、ジョブズのスピーチがどうなっていたのかを振り返ってみましょう。
まず一回目にメッセージを伝える時には、スピーチの中で話題にした本の最終号の裏表紙に登場する言葉として、そういう言葉があるんだという形で紹介しています。
こうした形でメッセージを登場させることで、聞き手としては興味がわいてきます。
次に、二回目に伝える時には、その言葉を繰り返したうえで、ジョブズ自身がどう思っているのかということが続けて語られます。
こうして聞き手の中には、共感が生まれてきます。
最後に、卒業生へのメッセージとして、「ハングリーであり続けてください、愚か者であり続けてください」と締めくくることで、このメッセージを聞き手と共有しています。
こうした反復のやり方を参考にしながら、さりげなく三回繰り返せるようになれば、あなたのメッセージを伝える力は飛躍的にに高まることでしょう。
普段の自分の表現の中で、「なんかインパクト薄いな」「すぐに忘れられてしまっているような気がする」といったことがあるようであれば、反復法を意識的に取り入れてみるというのもいいかもしれません。